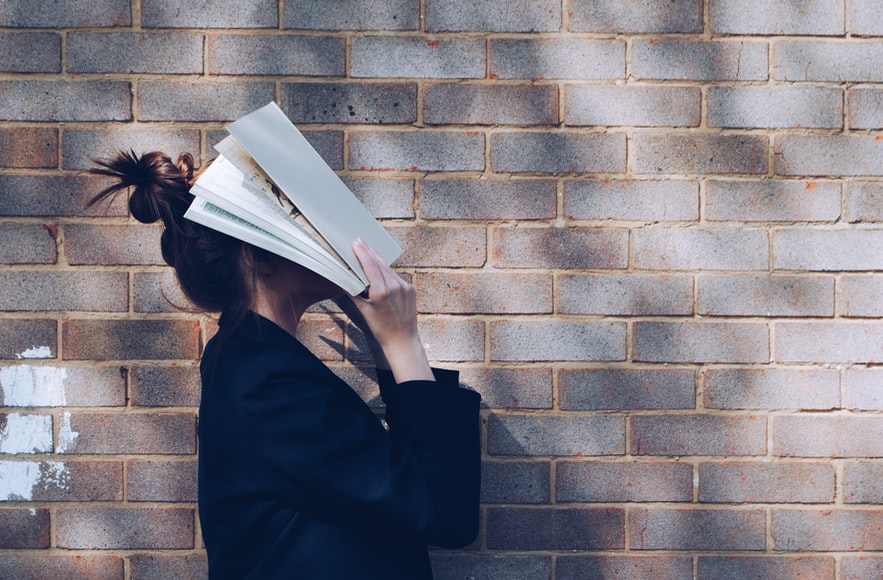こんにちは。すずきです。(@seiz_suzuki)
英語の先生を9年もしていますと、

という人を目にします。
これは僕の経験と照らし合わせても、

と思ってしまいます笑。
それくらい、日本に住んで英語を勉強している人にとって、英語をしゃべるということには非常に高いハードルがあることがわかります。
今日は、そんな英語を話すことが苦手だった英語教師である僕が、英語を積極的に話していくべきだと思う理由をお伝えしていきます。
英語がしゃべれないのは当たり前
まず、大前提として僕ら日本に住んでいる英語学習者が、英語をしゃべろうなんて無理があります笑。
ネガティブな意味で言っているわけではなく、それくらい難しいことだということです。
- 10年そこいらしか勉強しておらず、
- 普段英語を話すことなんてないのに、
しゃべれるわけがありません。
しかしなぜか、人前で英語をしゃべろうとしますと、
- 「自然な英語じゃないかな?」
- 「自分の文法…間違ってないかな?」
と、過度に心配してしまい、しまいにはしゃべらなくなってしまいます。
僕も同じ道を通りました。
- 留学経験はない。
- 帰国子女でもない。
- でもそこそこ英語は学んできている。
という状態で、周りに帰国子女やら留学経験者がいたので、自分の自信は地の底まで落ちてしまいました笑。

とわかっていても、実際に英語を話そうとなると「言葉が出てこないこと」は何度もありました。
その気持ちが変わったのは、以下のような事実を知ってからでした。
ネイティブだって間違える
大学院で英語教育の研究をしていた時、ふと、

と思って調べたことがありました。
例えば「common」(共通の)という単語がありますが、音節の数から考えると比較級はcommnerになります。
しかし、ALTが会話の中で「more common」と使った時、僕はジョークで、

とツッコむと、笑っていました笑。

と。

と英語のネイティブに聞いたリサーチがありまして、実際その結果は二分されていました。
Googleでいくつか調べてみても「音的にいいほうを使う」と書いてあります。
僕がよく聞くのは「more common」のほうかなという印象です。
日本語でも曖昧な表現やどっちつかずの表現はたくさんあり、だからこそ僕らは、
- 広辞苑
- 国語辞典
を使います。
日本語でも知らない単語や聞いたことのない単語はありますし、僕らも間違いながら気にもせず強引に会話を進めることはよくあります笑。
言語においては、その言語を使う大多数が使っている表現であれば、それは正解となります。
そういう意味では、正解はないですし、後々新たな正解が作られることもあります。
以下の表現はよく取り上げられる日本語の誤用例です。
- 「全然違うよ」
- 「あいつは姑息なやつだ」
- 「わかっててやるなんて確信犯だ」
- 「案が出てこない…会議が煮詰まってきた」
これらの表現は、使用法を間違えています。
それでも、みんなが使えば正解になります。
ネイティブだって間違えながら使っているのは、日本語も一緒です。
僕ら英語学習者が間違えるのは、何も変なことではないのです。
だから、積極的に話して間違えて良いのです。
ネイティブの知識レベルも人それぞれ
勉強大国の日本にいますと、テレビでクイズ番組が取り上げられるように、頭の良し悪しを競うことが文化として定着しています。
そこかしこで「学歴」を振りかざす人がいるように、
- 知識量
- 会話の内容
- 頭の回転スピード
による「合う合わない」は、人付き合いにおいて1つの指針となります。
つまり、英語のネイティブにおいても、「英語」それ自体に、
- 気を使って話をしている人もいれば、
- 適当なツールとしてだけ使っている人
もいます。
それは教育の格差が原因でもありますし、話し手の意識の問題でもあります。
そのギャップを埋めながら意思疎通を図ることが大切なのです。
日本に置き換えてみれば想像は容易で、
- 勉強や学ぶことが好きで知識のある人
- 勉強が嫌いで、あまり語彙の量がない人
など様々いることがわかります。
「どちらが良い/悪い」の議論ではなく、それが事実だということです。
もしかすると、英語を熱心に学んでいるみなさんのほうが、
- 徹底した文法を使っていたり、
- ネイティブも知らないような単語を知っていたり
するのかもしれません。
だから、

という言葉は、どうも「つかみどころのない目標」にも見えます。
それよりも、
- 「コミュニケーションツールとして」英語を使っていくことを手段とし、
- 英語を使って世界中の人々と理解し合うことを目的とする。
このカタチのほうが、「意味のある英語学習」を継続していきやすいと思っています。
積極的にしゃべりながら修正していく
ただし「ネイティブでも間違える」という事実を後ろ盾として、

という考えを捨てないまま、成長を続けないこともまた違います。
もし英語力を伸ばしたいのであれば、「間違っている部分」=「違和感のある表現」を直していかなければならないからです。
大切なことは、
- 「言語」はネイティブでも使い方を間違えるけれど、
- 彼らが使っているように自分も操ってみたい。
と思うことです。
まずは「間違えて当然なのだ」と思えれば、話すことに抵抗がなくなってきます。
そして話していく中で、たくさん間違えて、修正していきましょう。
みなさんの英語を前向きに直してくれる人がいる場合は、その訂正を素直に受け入れ、どんどんネイティブに近い英語に寄せていきましょう。
一方で指摘ばかりをしてきて、やる気を削いでくるような人とは、離れてしまいましょう。
気にする必要はありませんし、その人も必ずどこかで間違えています。
みなさんも、逆の立場に立てばわかります。
日本語を一所懸命勉強している人がいて、その人の間違いを指摘する時、

という気持ちから指摘するでしょうし、応援したくなりますよね。

と思う人はいないでしょう。
だから、みなさんも積極的に人前で英語を使っていいのです。
指摘されたら直せばよく、しゃべっていく中で修正していけばよいのです。
誰だって間違えるのが言語です。
「気持ちの問題」というよりも、いろんな視点から「言語をしゃべることの意味」を理解し、適切な形で学習を継続していくことが大切だいうことですね。
おわりに
僕は、
- 性格
- モチベーション
を信じていないように笑、「英語をしゃべる/しゃべらない」は、まずは「言語とはどういうものなのか」という事実を知ることからのスタートだと思っています。
特に「日本語に置き換えてみると」という考え方は、どの英語学習者にも伝わりやすいため、よく引き合いに出すようにしています。

とわかれば、積極的に話せるようにもなりますし、モチベーションだって勝手に上がってきます。
どんな意見があろうとも、英語で意思疎通を図ることは何も悪いことではありません。
間違えながら、修正し、英語を学んでいきましょう。
それではまた!