こんにちは。せいじです。(@seiz_suzuki)
最近はもはやスマホどころかSNSを見なくなったり、不愉快なニュースは見ないようになりました。
また、DaiGoさんの動画を見ていたら、

でプチ炎上していました。
法に関する岡野武志さんの動画も面白かったので、いくつか拝見させていただきました。
僕は、
- DaiGoさん
- ひろゆきさん
- 堀江貴文さん
- 西野亮廣さん
など、考え方が僕のような一般人には到底たどりつけない位置にいて、ズバッと言ってくれる人たちが嫌いではないです。
別にファンでもアンチでもなく、勉強のために拝見させてもらっております。
サブスクもオンラインサロンも入っていませんしね。
この方々が全てではないですし、やはり最終的には自分で情報を収集し、納得できる思考までもっていくことが大切だと思っています。
ネット社会でどのように立ち振る舞っていくのが良いのか、僕なりに考えてみました。
あくまで一意見
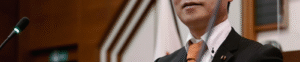
インフルエンサーや有名人の方々がはっきりと断言することはありますし、これが専門家となるとしっかりとしたご意見になるかと思います。
ただ、テレビやネットに出ているコメンテーターや自称専門家と呼ばれる人たちにも、「間違い」は必ずあり、

と思って見るくらいがちょうどいいです。
実際、僕も間違えることありますし、誰だって間違えの1つや2つくらいはあります。
「誰かのもとに映像が届く」ということは、どうしても自身の意見を画面越しに伝えているように見受けられてしまいます。
これがみなさん、
「自分が友達とあーだこーだと議論したり意見を出し合っている時」
に、
- 周りの人間にその議論が見られ
- いきなり何か突っ込まれる
としたら、恐くてなかなか意見を言えなくなるのではないでしょうか。
だから僕は、画面上でみんな(著名人)が好き勝手自分の意見を言っているというようにとらえています。

とはよく言われることですが、
- テレビに出ているから正しい
- 専門家が言っていることはすべて正解
- 有名人が使っている商品だから間違いない
- せいじの意見は全て間違っているしクソだ
と考えるのは、一旦待ったほうがいいと思っています。
論文や専門書を読んで勉強してみたり、ウェブ上でいいから情報を2〜3つ調べて見たり。
はたまたまず鵜呑みにしてから試しに一度行動に移してみたり、商品を実際に買って試してみたりするのも面白いかもしれません。
これらのような「過程」を自分なりに経たほうがいいのかなと。
そうすれば、



と感想や意見を持つことができます。
要は、そこに自分として確かな根拠や考え方があるのかということ。
一度、自分の思考や体験、リサーチや勉強を介しているのかが重要です。
一旦そのプロセスがないと、文字通りの「受け売り」となってしまいます。
彼らは彼らなりの経験や考えで意見を言っているのだから、それは僕ら自身も当然そうするべきです。
- あそこのメシはマジうまい
- これ使ってみたけどよかった
など『自分がそう思う根拠』というのは他でもない、自分しか持つことのできないものです。
聞いた話をただ他人に流しているのだとすれば、それはどこまで行こうと「彼らの」意見ですからね。
それを取り違えてしまった最たるものが、「アンチ」や「信者」なのかなと思っています。
盲信か叩き屋

ネット上で意見を言うなとは言わないのですが、やはり僕は、
「画面越しで起こっていることを画面越しから言うこと」
ほど、意味のないことはないのかなと思っています。
テレビやYouTubeにはどうしても撮影のウラがありますし、言っていることや意見が間違っていることも多々あります。
そこで、

とか、

と言う人たちがいますよね。
何もしないでリスクも取ってないのに、

と僕は常々思うわけです。
もちろん、発信者には「叩かれるリスク」が付き物なのは承知しております。
ネット社会において発信者に「コメントを甘んじて受け入れろ」と言うのも正論ですが、コメントをする側のリテラシーも大切だと思います。

は違うのではないかなと。
これは、盲信的に彼らの言葉を信じているからこその意見なのではないかなと。
ハナから、

と思っていれば、

となりますしね。(というかまず自分で調べろ)
それか、ただ叩きたい人ですかね。
ストレス発散なのかよくわかりませんが、コロナ禍では本当に多くの人が「叩き屋」となってネットに出現しました。
「暇が生んだ災害」でしたね。
人を叩いている暇があったら自分を磨きましょう。
不毛な言い合い
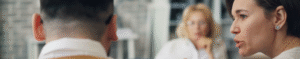
討論ではなく「言い合い」と言ったのは、コメント欄での争いがあまりにも不毛で非生産的だからです。
結論から言いますと、ここでの言い合いは基本的にスルーで大丈夫です。
何も生み出しませんし、外野が勝手に言い合っているだけの「居酒屋のおっちゃんたち」だと思って構いません。
まず「アンチ」と呼ばれる方々は、とにもかくにも「何とか難癖をつけたい」だけです。
粗探しのプロと言っても過言ではありません。
しかも自分の時間を割いてまで…もうほんとその熱心さに涙すら出ます。(お金をもらっている可能性も)
ゆえに一過性のものでしかありません。
これがファンたちとの大きな違いです。
- アンチは一時的なもの
- ファンは永続的なもの
として僕はとらえています。
激しい言い合いや罵り合いに持って行くことが、どれだけ意味のないことかとつくづく思うわけです。
消耗するだけですからね。
僕みたいにただただ動画を楽しみたいだけの一般人からすれば、そんな一過性に過ぎないものなんて本当に心の底からどうでもいいのです。
いちいち反応している時間が、もったいなさ過ぎます。
ぜひ『反応しない練習』をお読み下さい。
リンク
熱狂的な人たちが、
- 尊敬している人
- 自身の応援している人
をかばいたくなるのもわかりますが、どうせそんな「反対派の人たち」は1週間もすれば消えていきます。
むしろ、
- 自分がいつも見ている
- 自分がいつも応援している
方にお世話になったのであれば、「いつも元気もらっています」と感謝のコメントをするなど、変わらずその人を応援して楽しんでいけばいいのです。
イヤなコメントに不愉快になって反応しても、残念ながらメリットはないのです。
コメントの意味

SNSやネット社会というものは、多くの匿名の意見がもとになって築き上げられたプラットフォームです。
以前は僕も、よくニコニコ動画で実況動画を見ていたときは、
- コメントに笑わせられたり
- 建設的な意見に感心したり
したものでした。

と思えば、それはそれでロマンがあるというものです。
その人たちの意見も配信者やスタッフたちに伝わりますしね。
コメントも含めて動画を楽しんでいる人もいますから。
ここで大切なのは、自分のあるいは他人のコメントが、
- 建設的なものであるか
- 悪意があるものであるか
を見極める必要があるということです。
信者でガチガチにかたまってしまいますと、建設的な意見や前向きな批判にすら噛み付いてしまいかねません。
一方アンチコメントが集まりすぎると、精神的な攻撃が重なって、対象者を死に至らしめる可能性もあります。
だから僕は、ほとんどコメントしません。
するとしたら明らかに「ハッピーなコメント」しかできないですね。
とらえ方は人それぞれですし、対面じゃないため、コメントするのが難しいのです。
もし建設的・批判的なコメントをどうしてもしなければならないのであれば、かなり慎重になると思います。
それくらいコメントとは、威力のあるものなんですよね。
みなさんもお気をつけください。
おわりに
いろいろと考えてみたところ、やはりテレビや動画でハッキリとものを言っている人たちはそれだけで尊敬に値するという結論に達しました。
「自分はこうだ!」と思って信念を貫いていたら、ほうぼうから様々な意見が寄せられるのは仕方のないことなのかなと感じています。
リスクを取ってでもその場に立つことというのは、もちろんその分の見返りのためにやっていることですけれども、それだけでなかなかのメンタルだと思うのです。
その人たちに対して、様々な思いや意見を持つことは自由です。
しかし僕らが彼ら発信者ほどに、
- 学びが深くて
- 経験があるのか?
と言われると、残念ながら身を縮めてしまう思いになる人が多いと思います。
むしろそんな人たちは批判などせずに謙虚であるべきです。
発信者の彼らは聖者でも神様でもありませんから、僕らができることはそれを受けて参考にして自分で考えて成長する糧にすることくらいだと思います。
彼らに全体重をあずけてしまうのも危ないですし、批判ばかりしていても不毛です。
バランスよく、広く多くの意見を参考にしていれば自分なりの意見ができあがり、いちいちコメントに反応しなくなる、あるいは客観的に冷静にコメントに対処できるようになるはずです。
そうやって意見に客観性をもたせていくことが大切ですね。
そのためには日々、勉強と経験です。
それではまた!


