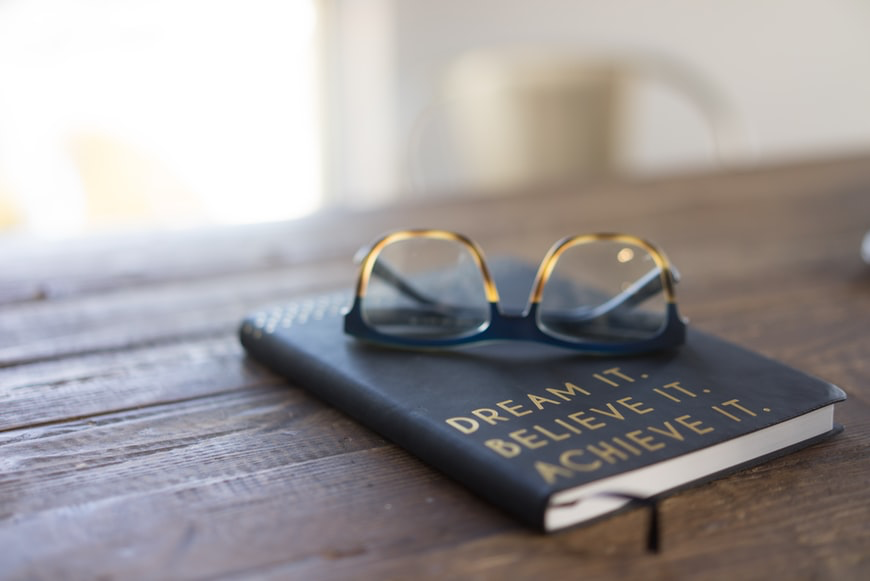こんにちは。すずきです。(@seiz_suzuki)
教員をやっていますと、生徒たちの「失敗」に直面することがあります。
僕自身、人の失敗を許さなかった人間でもありました。
今は自分がたくさん失敗していくことで、生徒たちに「失敗することの大切さ」を教えようと思っています。
さて、学校現場での特別指導(問題行動を起こして別室指導となること)とは、ある一線を超えてしまった「失敗」に対して注意を促す指導方法です。
先日もその処理だけで、ほぼ数日が消化されるという現象が起こりました笑。
- 生徒への指導
- 保護者への連絡
- 関係生徒への聞き取り
などのためです。
こういう時は「人として間違ったこと」はしっかりと注意すべきですからね。
では、僕はどのようにして問題行動を起こしてしまった生徒たちと関わっているのか。
書いていきます。
生徒たちの失敗を許してあげる
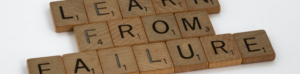
僕がまだ若くて駆け出しだった頃は、生徒の失敗を「鬼のような形相」で叱ったものでした笑。

と笑。

と思われるほど、怒りの感情が込み上げていました。
確かに、
- ものを壊したり
- 暴言を吐いたり
- 人に暴力を振るったり
人としてやってはいけないことまで、甘やかしていいということではありません。
そんな生き方はシンプルにかっこ悪いですし、指摘してあげなければ生徒の成長のためにもなりません。
ただ「特別指導」として別室で話していますと、ある程度の生徒は反省して理解もしています。
つまり、そんな状況で僕が怒り心頭に発する意味もわかりません。
当時は、

と勘違いをしていたのですね。
しかし、もう指導については完結しており、それ以上叱ったところで意味はないのです。
誤解を恐れずに言えば、

と、感情を一度切り離して考えてみましょう。
これはお子さんがいる方々にも効果的です。
- 失敗は失敗として認めて、
- 間違っていたら指摘してあげて、
- その後はフラットにしてしまう。
- (基本は褒めてあげるとGood!)
そうして子どもたちの行動を「僕らは見ているよ」と伝えてあげることが大切です。
失敗したことで、
- 人格を否定したり
- その子の存在を否定したり
してはいけません。
あくまで行為に対して注意をして、その後また生徒が成長することを信じてあげましょう。
生徒の成長を信じてあげる

人間誰しも、失敗の1度や2度、平気でやってしまうものです。
先生たちは「正義感」のカタマリですので笑、何度注意を受けてもわからない生徒に対しては、

と怒ってしまいます。
実際僕も、何度注意してもわからない場合は、

と言って「本気で怒ったフリ」をします笑。(ごくたまに大声も出します)
それでも心の底では、
「その生徒のことがキライ」
という気持ちになることはありません。
基本的には、生徒がいくら失敗しても次に頑張れるように背中を押してやるのが先生です。
もちろん、
- 欠席日数がかさんでしまったり
- テストの点数があまりにも悪かったり
- さすがに目に余る行為を繰り返したり
すれば、残念ながら学校を出ていかなければなりません。
ただ、もっておきたい基本のスタンスは、生徒の未来を信じてあげることです。
それがうまくいこうがいくまいが、僕らにできることはそれだけであり、成長にかけるだけで十分なのです。
まっすぐであれば間違っていてもいい

久しぶりの特別指導になってしまい、担任として疲弊したものの、生徒と保護者と話していると、なぜか込み上げてくるものがありました。
3年間も一緒にいますと、生徒は自分の子どものように思えてきますしね。
別に「生徒が悪さをしたから、それに対して悲しくなった」というわけではありません。
どんなに生徒が間違えても、生徒の担任は「僕」であり、責任の所在は保護者にも僕にもあると感じたからです。
「アニキ的存在」になれているのかはわかりませんが笑、指導が終わりますと生徒も保護者も、

と言ってくれます。
その言葉がどれだけ僕にとって重く、ありがたい言葉かは、担任をやってきた僕にしかわかりません。
それだけ感謝されていると同時に、

とも思いました。
そういえば昔、「ごくせん」という番組がありました。
青春コメディかつ単純なストーリーラインでしたが、教師を目指していた僕には大いにヒットしたものです笑。
主人公の仲間由紀恵(不良クラスの担任役)は、極道の家族の一員であり、筋の曲がった事が大キライです。
それでも、生徒のことを愚直に信じ、

と、熱血教師バリバリのコメントをします。
これは、今の僕にもガツンと響きました。
生徒指導で想いが込み上げてきたのは、その場面を思い出したからかもしれません。
確かに僕のクラスの生徒たちも、間違ったことばかりしてしまいます。
毎日のように僕に注意され、怒られ、次の日には忘れています笑。
それでも、
- 仲間想いで、
- とても真っ直ぐで、
- 今を一所懸命生きている。
僕はそのことをわかっているから、生徒を愛していますし、生徒たちもそれに応えてくれます。
大きく間違えなければ、後は勝手に走らせてあげたらいい。
たとえ見守っているだけであっても、子どもたちはそのことにちゃんと気づいています。

と伝えてあげて、生徒の失敗と成長を応援してあげましょう。
おわりに
特別指導とは、「担任の負担」が半端ではありません。
学校現場では、全てを担任に押し付ける文化がいまだに蔓延しています。
あまり賛成できる文化ではありませんが、これは一部正解だとも思っています。
「担任」というラベルは、適当につけられたものではないからです。
学校というチームで戦いながらも、最終的に生徒や保護者とやりとりするのは「担任」です。
そんな時に、
- 生徒の成長
- 保護者からの感謝の声
を見たり聞いたりしますと、もう気持ちが溢れてきてしまうものです笑。
生徒の失敗を見守り、成長する姿を送り出すこの職は、「教育」という意味では全国どこでもいつの時代でも必要な職なのかもしれません。
離れるのも愛おしいものですが、残りの期間も全力で生徒たちと駆け抜けていきます。
それではまた!