こんにちは。せいじです。(@seiz_suzuki)
先日、4年前に異動になった学校の、ダンス部の練習を見に行かせていただきました。
もはや先生でもなんでもない身分ですが笑、どうしても学校現場には特別な感情が入ってしまいますね。
ただ、

と感じたこともありました。
以前の僕であれば、ワクワクして学校現場に乗り込み、生徒とのやりとりを楽しみにしていたものでした。
今はもっとこう、「落ち着いた対応」ができるようになっていました。
今日は「生徒への熱量の伝え方」について書いていこうと思います。
現場で感じたこと

久しぶりに訪れたダンス部。
同僚から「様変わりしている」と聞いてはいましたが、第一印象は活気に満ちあふれているという印象でした。
僕は2つの学校(5年+4年)経験しましたが、どちらにも「それぞれの良さ」があり、こちらは生徒が生き生きとしていて、基本的には「頑張っている」と感じられました。
ただ5年間勤めた最初の高校でもありますので、「表層的な部分だけではない」のだとわかっていました。
部活動では頑張ることのできない生徒もいて、それは顔つきやダンスのレベルを見れば一目瞭然でした。
僕自身が高校時代に「燃え尽きること」ができなかったように、誰だって「ダルいなぁ」と思う時期はあるでしょう。
未熟な時の僕だったら、その生徒を問い詰めていたと思います笑。

とかなんとか言って笑。
でも今は、そういう感情よりも前に、
「部活動の組織として大丈夫か」
という点に目がいくようになりました。
中には一所懸命、真面目に活動に取り組む生徒もいて、むしろ「やる気のないオーラ」を出しているのは数名程度です。
その生徒たちに対して「お前はできていない」と指摘することが、果たして効果のあることなのでしょうか。

こんな風に思えたのは、2つの学校を経験して生徒との距離感が少しずつわかってきたからでした。
大切なのは、「僕ら大人の気持ち」ではなく「生徒たち自身の気持ち」であること。
- 彼らがどうしたいのか
- 彼らがどういう高校生活を送りたいのか
ここを大事にしてあげなければ、先生は務まりません。
長い付き合いの元同僚も、その点をとても大切にして顧問をしていました。
それにしても、
- 距離感をどう詰めていくのか
- 部活動をどう成長させていくのか
これらの点に関しては、

と思いましたね笑。
やる気のある生徒に集中

やる気のない生徒を問い詰めるのは、先生や親のやりたがることです笑。
先ほども書いた通り、一番大切なことは「生徒たちがどうしたいか」です。
生徒たちの気持ちを大切にするのであれば、「やる気がないこと」も尊重してあげるべきなのです。
- どうしても組織が壊れてしまう
- 明らかに組織に対して害を及ぼしている
そんな場合は生徒を呼びつけて指摘し、組織から追い出す必要があります。
ただ、「やる気のない生徒」は前任校でも見てきましたが、そこで叱ったところであまり効果がないというのが現実です。
みなさんも自分の学生時代を思い出せば分かる通り、やる気が出ない時は出ないものですし、それを指摘された時には逃げ場がなくなってしまいます。
僕ら教師がやるべきことは、もっと頑張っている生徒のために動くことでした。
やる気のない生徒へのケアも大切ですが、あまりにもそちらに「注意資源」を割いてしまいますと、「本当に大切なもの」を見失ってしまいます。
「生徒を諭(さと)して正しいレールに乗せること」
は、一見「先生たちの仕事」のように見えますが、実はそうではありません。
生徒たちは間違えることばかりですし、思春期の子たちがそんな単純になんでも熱くなれるわけではありません。
夢だって決まっていないですし、自分のやりたいことだってわかっていません。
だってみなさんもそうでしょう?
社会人になったって、

と考え直すことだってありますよね。
僕自身もそうでしたし。
だから生徒が思い悩んでいたり、やる気がなかったとしても、その点を指摘することに注力する必要はほとんどありません。
それよりも、頑張っている生徒を応援して伸ばしてあげること。
彼らを評価することで、やる気のない生徒たちが「どう変わるか」が大事であり、
- 何が大切なのか
- 何がカッコいいのか
を間接的に伝えるほうが有効です。
大人でもやる気のない人はいくらでもいますからね。
そこを指摘している暇があったら、自己投資して自分を磨けということです。
久しぶりに部活を見にきただけでも、そこまで感じることができたのでした。
生徒たちの未来を信じてあげること
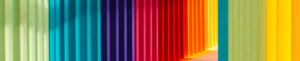
生徒たちの未来は明るい。
そう信じることができるようになったのは、彼らの若さや未熟さに惹(ひ)かれたからでした。
大人たち(先生や親)は、確かに一歩先を行っているかもしれませんし、子どもたちよりも長く生きています。
ゆえに、「多くを知っている風」ではあります。
ただ本当のところは、大人たちだって思い悩み、ツラい時間を過ごしています。
それは子どもたちと変わらないどころか、もっとしんどいことだってあります。
それでも前に進み続けるから、魅力的に映るのです。
僕たち大人が生徒の未来を信じてあげることは、
- 自分の未来を
- これからの世界を
信じることと一緒です。
以前の僕はそれができていなかったからこそ、「勉強や部活ができていない生徒」を指摘していたのかもしれません。
自分が頑張れていない時ほど、人を批判したくなるのですから、皮肉なものですよね笑。
完全に悪循環でした。
逆に、
「友人や生徒、仲間や他人の未来が明るくなること」
を願うこと。
これができた時に、人の失敗や未熟さを指摘しなくなります。
それよりも、

と思うようになるからです。
もしやる気のない生徒たちを見たとしても、
「彼らがいつかきっと、どこかで気づくこと」
を信じてあげなければなりません。
逆にそれができて初めて、生徒との信頼関係が築かれていきます。
ここに至るまでにはたくさんの経験と、素晴らしい同僚や友人たちの力が必要でした。
若い生徒たちだけでなく、僕ら大人たちも一緒で、
- 未熟で
- わからないことばかり
です。
それを認め、自分のできる部分を伸ばしていき、他人のできていない部分を許容してあげること。
生徒も一人の人間です。
ただ生きている年月が短いだけで、まだまだ足りていない部分は大人にもあります。
彼らの未来を、僕らの未来を、信じていきましょう。
おわりに
久しぶりに見た部活動。
最初は「指導の仕方」に辟易していたものでしたが、今は「生徒の未来に賭ける」という一択があるだけで、生徒たちだけでなく誰に対しても、優しく接することができるようになりました。
一見すると「無関心」にも捉えられますが、「他人を信じること」とは、ある意味自分の人生に集中することだと思っています。
それが回り回って、信じていた人に伝わればいい。
それまでは、僕は僕のできることを続けていくだけです。
自分の未来を信じていきましょう。
それではまた!



コメント