こんにちは。せいじです。(@seiz_suzuki)
先日書きました記事に関して、いろんな友人やお子さんを持つママさんたちと話してみました。
先日は久しぶりに小学生たちと交わりましたが、

という類(たぐい)のことを書きました。

と言われましたし、

など、いろんな意見をいただきました。
今日は改めて「僕の教育観」について書いていきます。
みんな人手不足はわかってる

ママさんたちや友人たちと話していますと、「人手不足」はこの業界に限ったことではないという前提があることがわかります。
教育、サービス、医療、政治…
それはなぜか。
当然、「成り手がいない」からです。
ではなぜ成り手がいないのか。
シンプルに、

という意見が多いかと思います。
教育に限って言えば、もちろんやりがいもありましたから、
- 行事
- 部活動
- 生徒や保護者との交流
などやってきたことは、今でも僕の糧となっています。

この言葉は、管理職からも出た言葉ですし、僕も現役の時は本当にそう思いながら指導をしていたものでした。
実は僕自身、わかりきっていたことがあります。

ということ。
そうなんです。
それが組織ですからね。
誰かが休んだって回りますし、補填されたり補完しながら進んでいきます。
なんでもいいから「回す/やる」がまかり通っているのが、学校現場(やその他の機関)なのです。
それが『問題だ』と言っているのです。
大事故なんてそうそう起こりませんし、なんとか回して何十年もやってきました。
そんなこと、重々わかってます。
それを知った上で、僕は9年間、幾度となく “組織” とぶつかってきました。
そうした「いろんな人のぶつかり」があったから、部活動も見直されてきているのです。
若かりし頃は、

と思い、何度も先生方とぶつかっては、管理職に報告を上げたものでした笑。
しかし当然のことながら、それでも変わらない現場。
他の若い同僚も声を上げてくれましたが、優秀な人ほどすぐに辞めていってしまいました。
そしてそこに疑問も持たずに、意見も上げずに、


という教職員方も、同時にたくさんいました。
だから僕も今回に限らず、教育現場では死ぬほど噛みついていました。(想像できます?笑)

- なんとしてでも
- 人手が足りなくても
やり切るしかなく、「やめる/縮小する」という発想はありません。(やっと部活動に対しての措置が出てきたくらいです)
僕はそうした先生たちにも、イライラしていたものです。(どんだけ笑)
先生たちがその事実を一番わかっているのに、変わらない現場にい続け、勝手にしんどくなる。
だからネガティブな意見が生まれ、人が辞めてゆく。
なんとなく毎日の仕事や行事を回しながら、

と、疲労やツラさを蓄積してゆく。(もちろん、本当にツラい方や仕事を楽しんでいる方もいます)
この悪循環を断つには、もっと根本から変えていかなければなりません。
ただ、僕の9年間ではやはり、できなかった。
力のない、一教員でしかなかったからです。


なんて関係ありません。
生徒観の問題ではなく、管理や体系の問題だからです。
それにこれからも、僕が現場を変えてゆくことはできません。
それは「わかりきっていたこと」だったのです。
イライラしなくなった自分

さて、そこから「離れる」という決断をしたのは、それが何より僕にとっての解決策だったからでした。
もちろん、心地の良い人は残っていたらいいですし、いろいろと事情はあることですから、何も「辞めたら正義」だなんて思っていません。
今回も優秀な小学校の先生たちに(というか組織や人員配置に対して)意見(「人手がなんとかなりませんか?」)を言ってみましたが、

と思い、

と反省しました。
僕も小学校関係の教育は人よりかなり経験がある方だと思っていますが、それでも小学校の現職の方ほど経験があるわけではありませんからね。
僕の他にもボランティアの方はいて、経験のある方もいれば経験のない方もいらっしゃいました。
ただ、経験のない方も一所懸命、その方なりに気づいた問題点を指摘していました。
これを、

と言っていたら、なんのための反省会だったのかわかりません。
参加した人の意見を無下にしていたら、本当の意味で変わることはないでしょうから。
僕もそこで感じたことを率直にお伝えしましたが、それ以上意見を言わずに踏みとどまったのは、

という意気込みで、小学校のボランティアに来たわけではなかったからです。(当然)
それは現場の問題であり、僕が意見すべきことではありません。
ただ僕が現場にいた頃は、

と、ちゃんと声を上げていました。
そうやって「おかしいことにはおかしい」と伝えていました。
今回も伝わらないとわかっていたとは言え、

という気持ちだけを伝えて、反応を見てみました。
案の定、

という空気感でした。

と思い、それ以上意見しませんでした。
イライラしていた頃(現職で意見を言っていた頃)というのは、

という願いが強かったからでした。
9年間やってみたものの、当然一人の教員が大きな組織を変えられるわけがありませんでした。

それから、
- 変わらないこと
- 変えられないこと
にイライラすることはなくなりましたね。
僕にできることなんてない
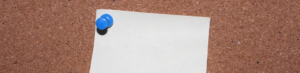
これは以前にも書きましたが、

そう思っていました。
彼らは彼らなりに努力をし、自分の夢を掴むため、巣立っていきました。
同じように、

と感じました。
決して悪い意味ではありません。
- 長い歴史
- 古い体制
- 閉じられた組織
とは、学校に限らず変わるのに長い時間を要するのが普通だからです。(多くの職員、社員さんがいますからね)
僕一人で変えられるものではありませんでした。
組織の中にいた時は、しっかりと生徒一人一人と向き合うこともできたとも言えますし、逆にできなかったとも言えます。
別に場所や役職に限らず、僕はいつまでも生徒たちと向き合っていくのだと思います。

それが僕のスタンスなのです。
- 組織にいるから、多くの生徒を変えられるというわけでもない
- 個人でやるから、目の前の人の人生を変えられるというわけでもない
ただ、目指す未来はどちらも一緒だということ。
どちらが良いとかではなく、
- 自分の合う場所
- 自分なりの花を咲かせられる場所
で頑張ればいい。
僕が「自分のいた体制(組織)」に対してよく意見するのは、決して組織を変えたいからではありません。
世の中の公教育に従事している人への提案であり、それを良しと取ろうと悪しと取ろうと、それもまた個人が決めればいいことです。
「その教育観」を発信した上で、自分で思考を整理し、僕はどうしたいのかを考えていきたいのです。
いつでも僕は、教育のことしか考えていません。
しかし、直接教育機関に働きかけられないことがほとんどですし、周りから見たら、

と言われるかもしれません。
それでもいい。
- 昔、中にいて
- その後、外に出た人
の意見くらいで受け留めてもらったらいい。
僕は僕なりに自分の教育を貫いて、いろんな生徒さんに価値を提供していき、その是非は生徒さんたちに決めてもらえばいいと思っています。
おわりに
- 仕事が厳しい
- 変わる気がしない
- それでも無理をするから疲弊する
- 疲弊するから教員の職から人が離れる
というこの流れは、教員の誰もが認めていることです。
先日も、小学校教員の友人から、

と、メッセージが来ました。

とは思いますが、そこに「期待」を寄せてはいけませんよね。
僕は幸いなことに、その中で楽しさややりがいを見つけることができました。
一方で、それを見出せないまま、辞めていってしまう人、あるいは幻滅してしまう人も多いです。
僕に組織を変える力はありません。
ただ、僕は僕なりに、とても小さな場面で頑張れればいいのかなって、そう思っています。
それではまた!


