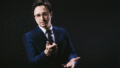こんにちは。せいじです。(@seiz_suzuki)
朝活やらブログやらをしていますと、必ず誰かと「食い違うこと」があります。
しかし、それは発信しているからこそであって、どうしてもこうした衝突を避けたければ「発信をしない」に越したことはありません。
例えば芸能人やインフルエンサーが炎上したりするのも、

と言えます。
とはいえ、それを言い始めればキリがありません。
世の中にいる限り、必ず「100人から好かれる人」とは存在しません。
今日は、そんな発信者が「客観性を持つこと」について言及していきます。
自分は絶対正論?

朝活のホストをやっていたり、こうして発信をしていますと、どうしても、

となりがちです。
ここで難しいところは、その「按配」です。
僕がブログを書き始めた頃は、断定をするのが苦手でした。

と笑。
読んでいる側からすれば、

となりますよね笑。
だから、ある程度は「断定的に」書かなければ、ブログで自分の思いを綴っていることにはならず、それは周りからの批判を喰らわないように書いているだけにすぎません。
それではこのブログの意味がありませんよね。
一方でそれが行き過ぎた場合、
- 反対のコメントは徹底的に無視
- 自分は絶対に正しくて間違ったことは言っていない
という思い込みに囚われてしまいます。
それではいけません。
Xやインスタ、このブログもそうですが、僕は必ず返事やコメントに目を通すようにしています。
それが「ただのいちゃモン」なのか「生産的なコメント」なのかは、自分で確かめればいいこと。
どちらにせよ、

と思うことそれ自体は、大切なことです。
これができない人ほど、拗(こじ)らせてしまうのではないのかなと。
- 自分の意志や軸がブレてはいけないし
- 同時に周りの意見もしっかりと取り入れること
が大事なのかなと。
いつでもバランスですね。
これができますと、「自分至上主義」が薄れていきます。
発信者も聞く側も

かと言って、

ということにはなりません。
現在では日本の政治状況が不安定であることから、XやYouTubeでのレスバトル(コメント欄での言い合い)が多く、匿名による誹謗中傷も目立ちます。
しかし2022年の法改正により、法的措置を取れるようになったおかげで、発信者情報開示請求ができるようになりました。
これによって個人を特定し、裁判にかけることができるようになったのです。
つまり、現在では返事をする側にもリスク(≒ 責任)があるということですね。
例えば、アカウントを消して逃げようとする人もいますが、その程度では逃げ切ることはできません。
一度してしまった投稿や誹謗中傷は撤回することが難しく、2000年頃からネットを使い始めている僕は、その点は十分に注意しています。
こうした「発信者側を守る権利」も整備されたことで、

という構造が出来上がりました。(事実上、匿名ではないということ)
もちろん、僕自身(=発信する際)も不適切なことは発言しないように心がけています。
多少の思想や考えが入る分には「表現の自由」がありますし、特定の個人を誹謗中傷しないことや、デマを流布しないことは大前提です。
- 発信者側も
- 返信ができる立場にいる側も

という時代ではなくなったということ。
正義は人の数だけあるでしょうし、文化や言葉遣い、礼儀なども日本国内ですら多種多様です。
それを認め合うためには、

という狭い考え方を捨てることですね。(自分の意見を強く言うこと自体は問題ない)
考え方を広げるには、
- 本を読む
- 人と話す
- いろんな経験をする
ことが大事です。
僕も決して偉そうなことは言えませんが、世界を回っていろんな人や文化に触れてきたことで、

というレベルにまで達することができましたね。
客観性を保つために疑う

僕は自身の英語学習もそうですが、反論されたり批判された場合は、気に留めすぎることはありませんが、


と、50%くらいの力で考えるようにしています。
昨今では、
- 政治家
- 専門家
- ニュース
- インフルエンサー
が言うことは、どれも改めて自分で調べる必要性があり「ファクトチェックができるサイト」などもできているようですが、正直これ自体も疑ってかかる必要があると思っています。(所詮人間がやっているため)

これは以前の記事でも書いた通り、

というのが、僕の見解です。
だからこそ、いろんなソースから事実を調べ上げるしかありません。
歴史の教科書だって、今まで信じてきた年号が変わったりしますよね。
新たに有力な文献が出れば、そうした歴史観も覆(くつがえ)るでしょうし、

と言う発見が、これからも出る可能性は否めません。
「正しい」と思ってたことすら、こうして変わってしまう世の中なのですから、

と言ったとしても、別に間違いではないでしょう。
そんな僕自身も、

と思っている文法事項や知識があっても、

ということはザラにあります。
客観性を養うために、読書をしたり人と話をしたりすることもいいのですが、そもそも論として、

という態度をとっていては、どんな経験を積んでも、その人が変わることはありません。
- 自分の言うこと
- 相手の言うこと
に対して、常に疑問を問いかけることで、

と思えるもの。
相手においてもそうです。
そのためにはたくさんの事実を確認し、その事実も全部鵜呑みにしないこと。
そうやって「疑うこと」を続けることで、客観性は磨かれていきますからね。
おわりに
僕も朝活でホストをしていますと、結構言いたいことを言っている自分に気が付きます笑。(別に誹謗中傷ではない)
面白いことに、周りの友人たちも100%賛同するわけではなく、いろんな意見を提示してくれたり、

と話をしてくれたりもします。
正解はないからと言って、フワッとしすぎて軸がブレてもいけませんよね。
常に自分を俯瞰しながら、意見を構築していきましょう。
それではまた!