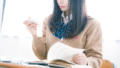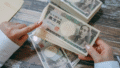こんにちは。せいじです。(@seiz_suzuki)
僕は今、朝活を行なっています。
朝活に限らず、何かを取りまとめて運行しようとしますと、どうしても「先生気質」が出てしまいます笑。


と、少しは気を使っているものです。
もちろん、神経質になっているわけではありません。
ただ、いろいろと配慮すべきことはあるなとは思っていまして、それが自然と出てしまうんですよね。
今日は僕が「どう周りを見渡しているか」について書いていきます。
ホストとしてあるべき姿
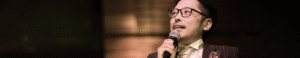
先生をやっていた時もそうでしたが、いつの間にか周りを見たわすという習慣(というよりクセ)が身についていました。
クラスを見渡せば、
- 一人の生徒
- うるさい生徒
- どんなグループがあるのか
など一目瞭然でわかります。
大人になってもそうでして、若い頃ほどの明確な線引きはないにせよ、

と、少しばかり俯瞰して見るようになりました。
例えばグループの会話がうまくいっていなければ、ホストとしてそれを “ある程度は” 取り持つ必要があります。
あまりにも放置してしまいますと、

となり大人(参加者)同士とはいえ、対立が起こります。
「全てを把握して、事前に火消しに回ること」
はできませんが、ホストとして最低限やるべきこととは、それなりにあるとは思っています。
「全く何も気にしない放置ホスト」
よりも、
「気を配るだけとは言え、周りを見ているホスト」
では、後者のほうがいいに決まっていますからね。
僕はできる限り「適当に」ものごとを進めたい派ではありますが笑、やはり最低限の気遣いはしてしまうようです。
- ちょっと僕がイヤだなと思ったり
- 参加者から些細なクレームが入ったり
したら、できる限りすぐに対応しようと思っているのです。
そういうこと(=ある程度の法整備やルール)ができないグループやコミュニティからは、いずれ参加者が離れていってしまいます。
それは「やっている側」の僕としても本意ではありませんから、無意識のうちに気を使って最悪の状況を回避しようとしているのかもしれませんね。
自分の匙加減でいい

とはいえ、あまりにも気を張りすぎていますと、
- かえってやりづらくなったり
- 面倒くさくなってやめてしまったり
することにもなります。
どこまで行っても「明確なルール」なんてものはありませんが、最終的には、
- ホストの按配
- 空気感の作り方
- ベクトルの持っていき方
によるのかなと。
何かの中心に立ち運営をしていこうと思いますと、ガチガチのルールや気遣いがある限り、なかなか続いていきません。
僕は、「自分ができなくなったら終わりだ」と思っていますから、

と決めています。
- 最低限の配慮はあるが
- 無理が生じないようにする
そうしなければ、この朝活も1年以上は続きませんでしたからね。
ここまで、僕がまるで「人に配慮ができている人」のように見えているかもしれませんが笑、実は「適当さ」も兼ね備えておく必要があります。


と、「参加者たちにも裁量権がある」かのように見せておくことです。(実際にある程度はあります笑)
この「緩(ゆる)さ」と言いますが、少し余白があったほうが、柔軟に対応できるのです。
ある程度「大人同士」ですので、彼らに裁量権があるほうが、いい意味での「気遣い」になることもあります。
「ここ」を探り続けていますと、

という結論が出ます。
高校教員の時もそうでした。
なりたての頃は、

とヘンなことを考えていましたが笑、高校生たちは昼食時間に先生に邪魔されず、“自分たちの時間” があるほうが嬉しいわけです。
こうした按配とは、確かに学校の先生という「集団をまとめる経験/集団との距離感の経験」が、あったからこそなのかもしれませんね。
周りに対する配慮とは?

さて、僕がまるで「周りが見られる人」みたく見えていますが笑、正直そんなことはありません。
僕の言っていることが伝わらないこともありますし、正直、離れていった人もいました。
別にそこに対して落ち込むこともないですし、いまだに朝活に「来る人/来ない人」はまちまちで、

と言っています。
「配慮」とは聞こえがいいものですが、実際は、

というマインドを持っておく必要もあります。
先ほどの「適当さ」に通ずる点ですね。
これを「独裁」と言う人がいるかもしれませんが(実際そんな人はいませんが)、

と問いたいですね。
ある意味、こうした反応とは一種の「ルール」でもあります。
僕がホストをやっている以上は、ヘンなことをする人は排除(回避)する他ありません。
「配慮する」とは「誰か一人のためにみんなが我慢すること」ではありませんからね。
それだったら、

です。
人間同士ですから、わかり合えないこともありますし、
- 生理的に受け付けない人
- 考え方や思想が合わない人
もいます。
僕はオンラインの授業でも、そういう生徒さんと話すことはありますが、

と、自分の軸は譲りませんし笑、一方で、

と、相手を変えようとすることもありません。
もちろん、頑固になって柔軟さを失っていてはいけませんけどね。
僕が言いたいこととは、


ということ。
妥協し続けてしまったら、いずれは僕や友人たちの「やりたいはずのこと」ができなくなってしまいますからね。
そうした「毅然とした態度」も時には必要。
ただ、基本的には武士道の精神を持っておきながら、冷静に対処することですね。(いきなり武士道笑)
それぞれにはそれぞれの言い分があります。
うまく対処しつつ躱(かわ)しつつ、かつ時には厳しく接する。
この総合的な対処術こそが、「配慮」だと思うのです。
おわりに
配慮とは “聞こえのいい言葉” です。
僕も先生として「集団をまとめる時」には、いろいろと苦労しました。
いろんな「個人的で勝手な意見」が出てくるのはわかりますし、逆に僕自身も会議でいろいろと暴れ回っていたものでした笑。
だからこそ、そういう時は「僕なりに」まとめていけばいいだけのこと。
気に入らなければ修正していけばいいですしね。
これからもうまい按配でやっていこうと思います。
それではまた!