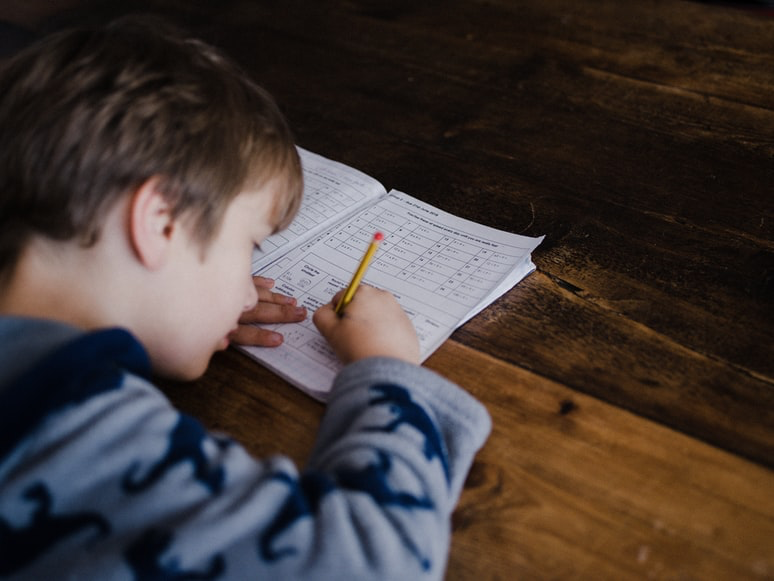こんにちは。すずきです。(@seiz_suzuki)
先日、後輩とカフェでまったりと話をし、さらにオンラインコミュニティでは英語学習について雑談をしました。
いつまでも学び続ける人でありたい。
そう思う僕は、昔から勉強が大好きです。
社会人4〜5年目あたりに英検1級を2回受け、2回落ちるなど笑、「まだまだやれるもんだなぁ」と感じつつも、どこかで「もういいや」とも思っていました。
その一方で読書の影響は色濃く出ており、知識もさることながら、
- コミュニケーション術
- 投資
- 考え方
- 人生論
- 心理学
などのありとあらゆる分野、それも実用的なものばかりを読んでいるため、友人と話すことで学んだことをかなりアウトプットすることができています。
そんな30代が、孤軍奮闘することを決心しました。
ここに決意文を残しておきます。
いつまでも学び続ける理由

ヘンリー・フォードはこう言っています。
20歳だろうが80歳だろうが、学ぶことをやめてしまったものは老人である。
学び続ける者は、みな若い。
これは単なる「勉強」を意味しているわけではないと思っています。
「机上で勉強したこと」の全てが活きる世界であれば、それほど簡単な世界はありません。
実世界においては、様々な意味での「学び」があります。
僕は「読書習慣」がついたことで、
- 自分の人生や世界に対する考え方
- 人との接し方や、人としてのあり方
- 悩みに対する具体的な解決策
などが身につきました。
友人知人と話している時は、自分の頭の中が整理されていると感じることも多くなりました。
以前であればいわゆる「5教科の知識」しかなく笑、
- 社会人なのにお金についての知識がない
- そもそもGIVEできるほどの知識や経験がなかった
- 世の中に対する考えも浅く人に対してGIVEをしようとしなかった
- 対人スキルについては「先生をやっているから大丈夫なはずだ」と思い込む
という状態でした。
「いつまでも若くありたいから勉強している」というわけではありませんが、そんな自分を顧みてみますと、社会人になってからいかに「学んでこなかったか」が見て取れます。
どちらかといえば、
- そんな自分に嫌気がさしたこと
- そんな自分に説得力を持たせたかったこと
- 何より、学ぶ楽しさに改めて気づいたこと
- 人にGIVEできるように学びを広めて深めたかったこと
これらの理由のほうが、学びを再開する強いきっかけとなりました。
- 右も左もわからない10代を相手に教えることは教師として当然のことですし、
- 近い世代の「同じ悩みを持っている友人知人」と話をすることで、自分も学びたい。
自分をアップデートしていくこと、成長していくことは何歳になってもワクワクしますし、純粋に楽しいです。
内面から魅力的になっていくことができますので、僕はいつまでも学ぶことを続けていきたいと思っています。
対人コミュニケーションでも役に立つ

先日、後輩と話をしていたところ「上司とうまくいかない」という悩みを聞きました。
教師である僕にとっては、「人の悩みを解決すること」は会話において最重要事項ですので笑、嬉々として話を聞きました。
変態と呼んでいただいて構いません。
僕自身も「人間関係における摩擦」に悩まされたことは幾度となくありました。
確かにこの時代、ネットで「えいやっ」と調べてしまえば「人間関係を良好にする秘訣3選!」みたいなものは出てきます笑。
しかし「本」という媒体には、なかなか勝つことができません。
1〜2冊程度の読書ではどうしても思考がまとまりませんし、偏りも出てきてしまいますので、あるトピックについては何冊か読むとよいでしょう。
「同じ悩み」というものは先人たちも持っているものでして、「誰もが持つ悩み」に関する書籍は多く出ています。
「死ぬほど」とまではいきませんが、ここ1年弱でだいぶ書籍を読みましたので、後輩にはある程度「こういうことなんじゃないかな?」と伝えることができました。
世の中には「最適解」や「絶対解」が転がっているわけではありません。
それぞれに悩みがあり、即効性のある処方薬なんてないのです。
ただ一方で、
- 普段から本を読み、
- 考え方を事前に構築しておく
ことで、自分の価値観の軸が定まり、様々な状況を対処することができるようになります。
例えば、
- 「マウントをとられる」→マウント合戦に入らず、そっと身を引く。
- 「嫌がらせを受ける」→基本的には距離を置くが、礼節さは忘れない。
- 「他人を変えることはできない」→干渉して自分がダメになっても意味がない。
- 「価値観が合わない」→相手の価値観を認めつつ、衝突を避け、かつ相手に流されない。
など、普段から多角的な意見を取り入れておくことで、柔軟に対応することができるようになりました。
「人としてのあり方」についても、自分が大切にしていることを常に意識しておくようにしています。
- 節制
- 鍛錬
- 礼節さ
- 清貧さ
- 足るを知る
- GIVEの精神
こうした「自分の軸」がありますと、会話する時にブレない自分でいられます。
学びとは何も「勉強」だけではありません。
- 一度自分と向き合い
- 本や友人・知人の価値観に触れ
- 人生について学び続けること
で、より魅力的な人になっていけるのだなと思っています。
具体的な学習も継続しよう

僕は英語教師ですので、ありがたいことに「目指すべき検定試験」は無数に存在します笑。



と、以前の僕も思っていました。
しかしこの勉強のプロセス自体に意味があることに気づきました。
- リスニングも難しいが、単純にリスニングの勉強になる
- 英検1級の単語は難しいけれど、時々ネイティブとの会話で出てくる
- TOEICも、受けることで『点数を伸ばしたい人』に教えるきっかけになる
- 簿記3級もFP3級も、その考え方を学んでおくだけで人生設計に役に立つ
実際、おかげさまで簿記3級は1度落ちたもののその後合格し、今でもお金の勉強の役に立っています。
僕は今回、僕は新たな決意をしました。
- 英検1級
- TOEIC(未知すぎる笑)
- FP3級
(その後、2022年中に1級を取得、TOEIC 900点、FP3級を取得しています)
を頑張ろうと決めたのです。(これもコミュニティのみなさんのおかげです)
同時進行は難しいので、順番を決めてやっていこうかなとも思っています。
どうなるかは自分のキャパ次第ですので、もしかしたら変わるかもしれません。
「意味がない」という言葉につきましては、実は僕も、この言葉は核心を突いていると思っています。
そもそも「合格したかどうか」「点数が〇〇だったかどうか」は、あまり意味がないと思っているからです。(昇給や転職に有利になるのであれば大切です)
それでも、「合格に向けて」「高得点獲得に向けて」学び続けることは有意義なことですし、そのプロセスの中で成長することが本当に価値のあることです。
以前は、
- 落ちること
- 失敗すること
- 間違えること
に、恥ずかしさを覚えていた時代がありました。
僕の周りには「優秀な友人が多すぎる」ため笑、引け目を感じていたのです。
しかし僕が、
- どれだけ落ちようが
- どれだけ受かろうが
- どのレベルを受けようが
周りには関係のないことです。
大事なことは、
- 失敗を繰り返してもいいからそこから学び
- 友人たちとプロセスをシェアし
- 自己実現に向けてひたむきに頑張ること
です。
何も臆することはありません。
いつまでも学び続ける人はかっこいい。
僕もそうありたいから、また頑張ろうと思うのです。
おわりに
周りの人に感化されてしまっている自分を見て、一番驚いたのは「自分」でした笑。
モチベーションなんて気にしたことがなかったからです。
しかし、仲間とともに頑張ることは、何よりも楽しいことです。
ひとりでも細々と、淡々と続けられるのが僕の長所でもありますが、人と一緒にコトを成し遂げようとすることで、やる気はさらに出てきます。
ぼっち30代。今こそ立ち上がる時です。
何年かかってもいいと言い聞かせて、頑張りたいと思います。
それではまた!